それは時雨のように、どちらともなくふらふらとおぼつかない気持であった。
涼しいと寒いの間でさまよう鳥肌の、迷った挙句にぞわぞわと、身震いにもならぬ震えに、どうにもならぬ煮え切らなさをたたえて、少年はそこから意識を逃れたいかのように虚空を見つめていた。
しかし逃れようとすればするほど、いっそ篠突く雨であれと、心が悲鳴をあげるのだ。
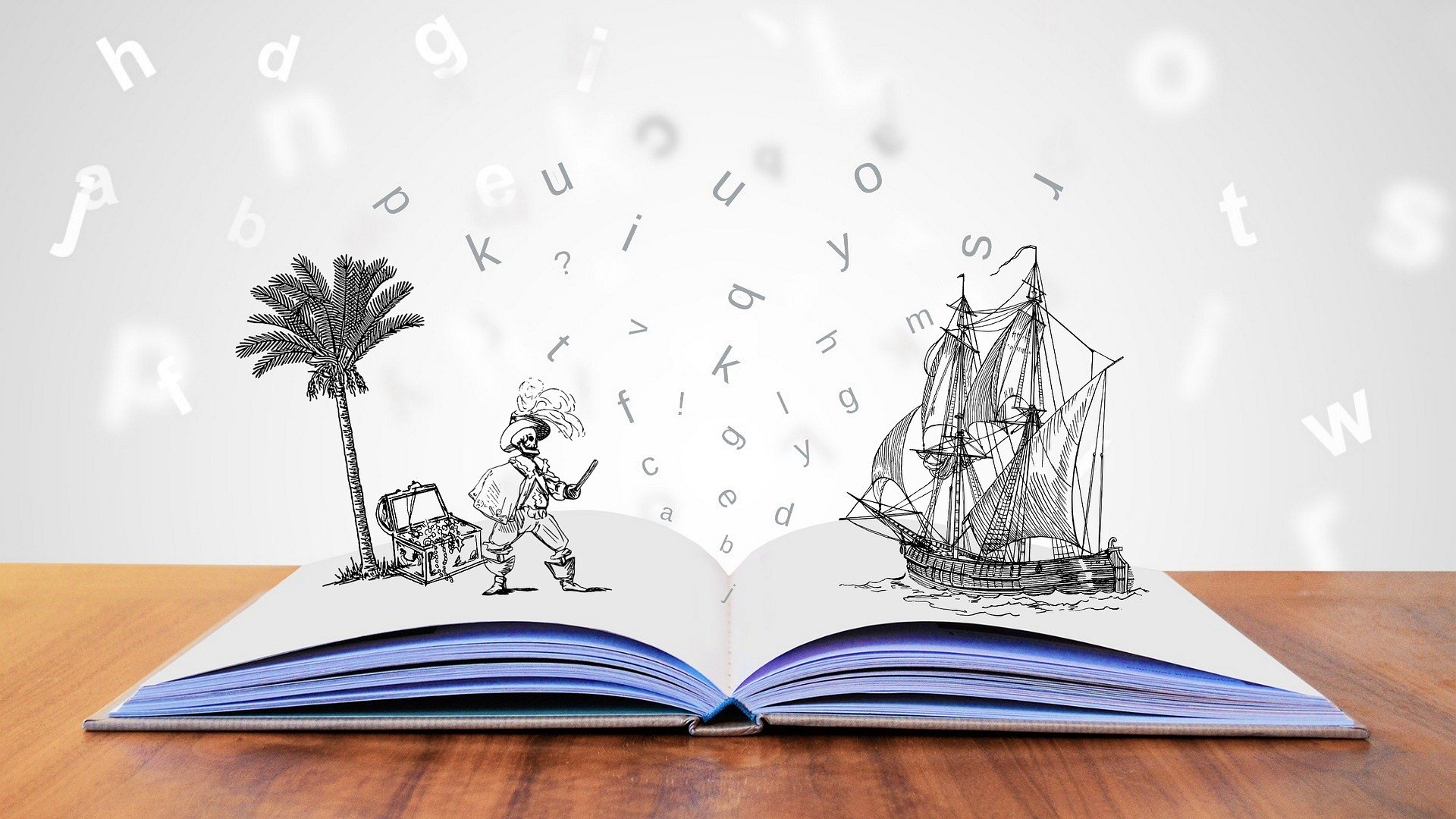 お話
お話それは時雨のように、どちらともなくふらふらとおぼつかない気持であった。
涼しいと寒いの間でさまよう鳥肌の、迷った挙句にぞわぞわと、身震いにもならぬ震えに、どうにもならぬ煮え切らなさをたたえて、少年はそこから意識を逃れたいかのように虚空を見つめていた。
しかし逃れようとすればするほど、いっそ篠突く雨であれと、心が悲鳴をあげるのだ。
コメント